Overview
この稿では、西洋と東洋。ふたつを「OS」として比べながら、
いま、どちらの声に耳を澄ますべきかを探ってみる。
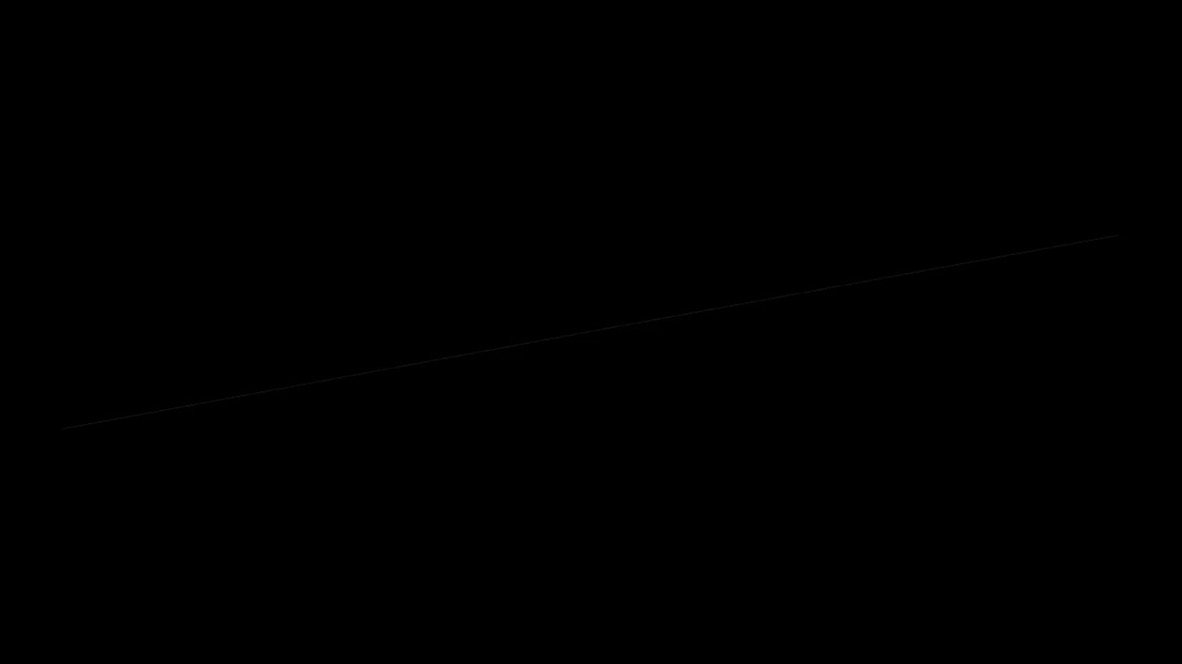
2025年。
世界は静かに、確実に
ロシアとウクライナ。
次にどこで、新たな火種が燃え上がってもおかしくない。
もう誰も驚かない。麻痺も始まっている。
共通するのは、
“正しさ”は、立場によるもの。
国が争うのか?
確かに一神教の思想は強い。
科学、政治、経済
私は思う。
この西洋思想的OSは、バグってるんじゃないか、と。
じゃあ、東洋思想はどうか?
常に沈黙していて、あいまいで、わかりにくい。
そんな世界の見方が、たしかにある。
合理性や効率を優先して生きてきたつもりだ。
だが、静かに振り返ると、
自分の中に、東洋的な何かが眠っている。
この稿では、西洋と東洋。
ふたつを「OS」として比べながら、
いま、どちらの声に耳を澄ますべきかを探ってみる。
|1|自然との関係性|「征服する自然」vs「共に在る自然」
速くて、無駄がなくて、機能的。
それが正しい、と信じてきた。
自然は、整えるもの。
いや、もっと正確に言えば「管理する対象」だ。
「都市は人間のための機械である」
光も風も、使えるものとして調整される。
だが、東洋の思想は違う。
自然は、制圧し管理する相手じゃない。
自分の一部だ。
風が吹き、雨が落ち、光が差す。
それに逆らわず、身を預ける。 そういう佇まいだ。
日本の建築には、それがある。
隣家と隔てるのは植木。
縁側は、家の中であり外でもある。
外と中の空間が緩やかにつながり曖昧だ。
古民家は言うに及ばず、
谷口吉生の東京国立博物館 法隆寺宝物館、
妹島和世のすみだ北斎美術館。
谷口は、建築物に多くを語らせず、
妹島は、建築物に周囲の景色を写し込む。
設計というより、むしろ調和だ。
東京という都市は、上から見れば西洋的だ。
人間の都合で整地されなかった
「何か」が、まだ残ってる。
自然を他者と見るか、仲間と見るか。
その違いは、数字では測れない。 体でわかるものだ。
目的もなく街を歩く時、
それだけのことかもしれない。
|2|知のあり方|「言葉で制する知」 vs 「身体で育む知」
そんな空気が、世の中を支配して久しい。
会議でも、授業でも、言葉が強い。
何のために、なぜやるのか。それを言え、と迫られる。
だが、そんなもので本当に“わかった”ことになるのか。
それは間違いだ。
知る、分かるというのは、もっと厄介なものだ。
東洋の考え方は、それを知っている。
頭じゃない。体で覚えるんだ。
それが「守」。
理屈じゃない。
身体に沁みて初めて、知識が“知”になる。
そして、もうひとつ。
禅の「不立文字」。
言葉じゃ伝わらない、という思想だ。
真理は、沈黙の中にこそある。
語らずに、ただそこに“在る”。
禅の坊さんたちは、それを体験として叩き込んできた。
考えるな、坐れ。
言うな、感じろ。
私たちは、学校や仕事で“説明する技術”ばかり磨かされてきた。
だが、心のどこかでは知っている。
それが、東洋のOSだ。
|3|自己と他者の関係|「主張する個」 vs 「滲み合う個」
会議でも、面接でも、SNSでも。
「あなたはどう思うか」が、
西洋の考え方では、
ひとりの人格で、筋が通っていて、
それが“成人”だと教えられてきた。
社会は契約でできていて、
だが、東洋の考えは違う。
人は、関係の中に生きる。
立場が変われば、自分も変わる。
母である私、部下である私、
友の前では少し違う顔。 どれも“本物”だ。
「分人」そう呼んだ作家もいたが、
そんな考え方は、ずっと昔から東洋にあった。
仏教の縁起、儒教の仁、道教の自然。
どれも、“人は関係性のなかで変化する”ってことを前提にしている。
東洋の人間は、語る前に踏みとどまる。
空気を読んで、言葉より態度で調整することもある。
それは、卑屈でも、逃げでもない。
他者と調和するという、もうひとつの強さだ。
もし自分を出すことに疲れているなら、
それが、東洋的な自己観というものだ。
|4|価値判断の軸|「言語化された目的」 vs 「佇まいの正しさ」
なぜ、それをやるのか。
世の中は、その説明を求める。
理由を語れ。数字で示せ。
目標と手段が合っていれば、 そ
れで正しい──そういう論理で動いている。
ビジネスの世界では、KPIやらROIやらが飛び交う。
“目的のためなら、この手段”と、 フレームワークで割り切っていく。
筋は通っている。
だが、妙につまらなさもある。
東洋の感覚は、少し違う。
なぜそれをやるのかと訊かれたら、
京都の老舗の商家は、そうやって続いてきた。
何百年も守り抜いた所作には、 理由なんかいらない。
そこに、謙虚な「正しさ」がある。
論理では測れない「佇まい」。
それを感じ取る力が、 この国の中にはまだ残っている。
西洋は「語れる価値」に強い。
ロジックで動く職場で戦いながら、
そんな日常の中に、
説明できないが、どうしても捨てられないものがあるなら、
それがあるなら、 まだ大丈夫だ。
|5|死生観と人生観|「抗う死」 vs 「還る死」
だが、それにどう向き合うかとなると、話は別だ。
西洋の考え方では、人生は一直線だ。
だから、そのあいだに何を残すかがすべてになる。
死は、抗うもの。 技術で、医療で、なんとか先延ばしにする。
だが、東洋の思想は違う。
川の流れのように、生も死もつながっている。
すべてが、そう言っている。
茶道も、禅も、老いを整いとして受け入れる。
「死を考える」ことは、生を深くすること。
禅僧は「念死」と唱え、
死に備えることで、生き方が研ぎ澄まされる。
祖母が言った。「そろそろ潮時かねぇ」
西洋が死を遠ざけようとするなら、
私たちがいま、生きているその足元にも、
柔が剛を包むとき
全力で打ち込んでくる相手の力を、
流れに身を預け、間を読み、
相手の力を“使って”制する。
そんなことが、この世界で起こるのか?
常に敵をつくり、勝ち続けようとすることに未来はない。
刚は暴れ回り、
柔が最後に、全体を制する。